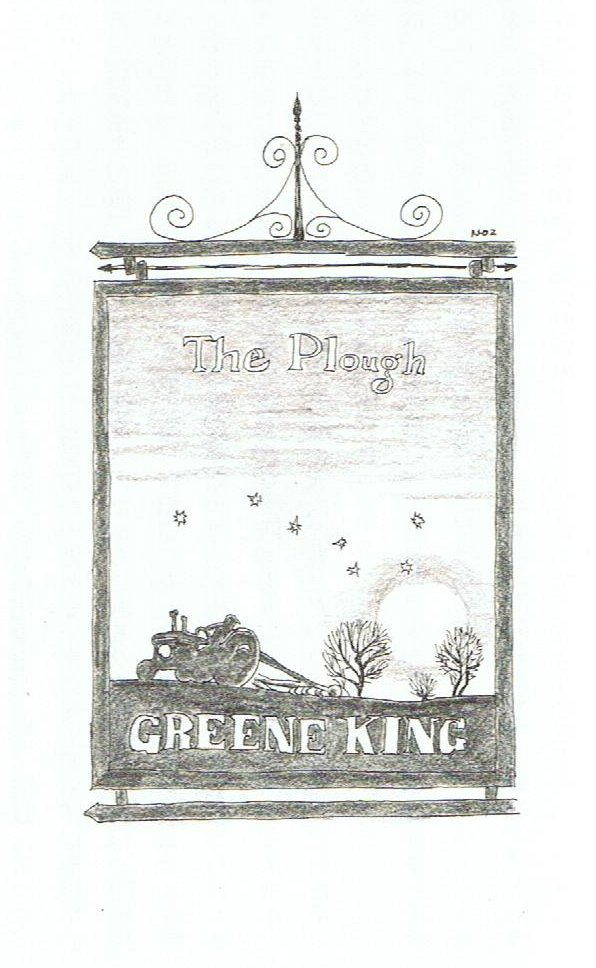

平凡社
庭冴ゆる月なりけりな・・・・・・・
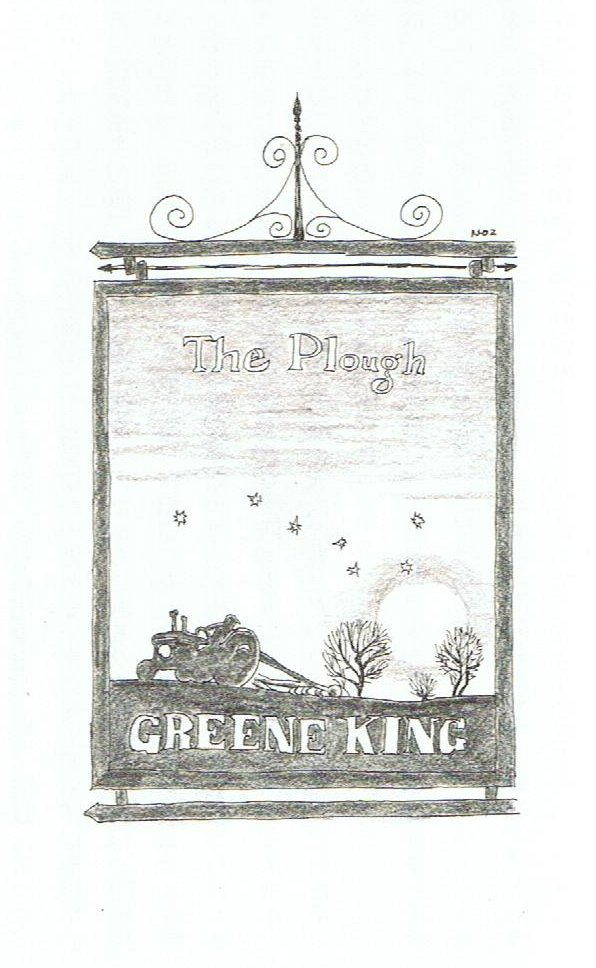 |
 平凡社 |
ルーシー・マリア・ボストン夫人が死んだ。一九九〇年の五月二五日のことである。
享年九七歳。年に不足はないといっても、私にとっては、美しいイギリスの思い出が、
どこか遠いところへ消えていってしまったような、悲しい出来事だった。何故と言って、
私は、今から六年ほど前、夫人の生涯愛して止まなかったヘミングフォード・グレイのマナ
ーハウス(荘園領主の館)に八ヶ月近く住んでいたからである。この館は一一二〇年に
ノルマン人によって建築されたという古く麗しい館で、夫人の代表作『グリーン・ノウ物
語』シリーズの中で、いつも変わらぬ舞台であった「グリーン・ノウの家」のモデルに
ほかならなっかた。水の澱んだ古い濠に囲まれた、四エーカーほどもある広大な敷地の中
にひっそりと立つこの古館に、当時九一歳の夫人と私とたった二人で暮らしていた幸い
な日々が、今も昨日のことのように思い出される。
夫人は、いつも優しく朗らかで、闊達に話し、大またでさっさと歩き、しょっちゅう冗談
を言っては「ウオッホッホ」と磊落に笑っていたのだったが。
私に美しい英語を教え、イギリスとイギリス人の「良さ」を味あわせてくれたボストン夫
人。それもこれも、今はみな遠い思い出になってしまった。さようならボストン夫人!
けれども、今から思えばそれはたしかに、ひとつの「物好き」には違いなかったのだ。
ヘミングフォード・グレイ村は、ケンブリッジの町から十二マイルほど北西にあって、自
動車がなければとてもケンブリッジまで通えるものではなっかた。では、なぜ私が、わざ
わざそのような不便なところに住むようになたか、そうしてそのゆえに「イギリスで最
も幸せな日本人」と呼ばれるようになったか、それは、少しの努力と大きな偶然と、それ
から、何よりも「物好き」のなせるわざであったろう。
それまで私は、ロンドン大学で古い文献を相手に半年暮らしていた。予定は段々と遅れ、
すでに十月の新学期がはじまっていた。伊勢物語ではないけれど、ロンドンにはあらじケン
ブリッジに住むところ求めにとて、はるばると二時間の道のりを運転して、私はケンブリ
ッジにやってきた。しかし、ケンブリッジは小さな町で、貸家の数も従って少なく、新学
期が始まるまでにおおかた勝負は付いてしまっていた。だから、私がのこのこと家探しに
出掛けたころには、良さそうな物件は殆ど残っていなかったのである。
いやな思いをして不動産屋のおばあさんに頼み込んで、いくつかの家を見に行ってみれば、
あるものは便所のぶっこわれた気の滅入るような陰気くさい古家であったり、または、ろ
くに台所もないような、味もそっけもない今出来のワンル−ムフラットであったりした。
しかも、不動産屋のばあさんの言うには、「そんな、アナタ、たかが四ヶ月やそこらじゃ、
サッテ貸す人があるかしらねえ・・・・・」と実に冷たい(当初は四ヶ月の予定だったのだが、
実際には延びて八ヶ月間そこにすむことになったのである)。所属のコレッジの部屋は
どういうわけかアメリカ人優先で、日本人には木で鼻をくくったようにそっけなく、何度
聞いても「部屋はありません」の一点張りであったし・・・・。途方に暮れるというのはこの
ことであった。
一日中あちこち探し回って、秋の短い日は既に老いようとしていた。
私は、疲れた足を引きずって、「Society for Visiting Scholars」という、ケンブリッ
ジ大学の一種の互助組織のようなオフィスを訪ねてみることにした。いわゆる藁をもつか
む思いで、そういえばそんなのが大学案内にあったなあ、と思い出したのである。大学案
内には、いかにも親切そうなことが描いてあったが、聞くと見るとでは大違いで、行って
みるとそこは、不親切も不親切、不親切の総本山のようなところなのであった。
黒く重い扉を開けて中に入ると、二人の中年婦人が、今や机の上を片付けつつあるとこ
だった。部屋を探しているのだが、と尋ねると、そのうちの一人が、これ以上面倒なこ
とはないというような渋面を作って、顎の先でそこなる書類の束を指すと、「そこにいく
らでもあるから勝手に自分で見て、これとおもうやつをメモでもして、あとは好きなように
自分で交渉しろ」と言った。何という不親切な不愉快なやつだろうと思いつつ、仕方なく
その書類の束をめくっていると、その背中に浴びせかけるようにもう一人の婦人が怒鳴った。
あと五分でここを閉めますから、もう帰ってくれませんか」
時計を見ると、四時二十五分で、なるほどあと五分でここが閉まる時間なのであったが、
それにしても、と心の中で舌打ちしつつ振り返ると、すでに女達は二人ともコートを着て、
出口の所で立って待っていた。その時、私はようやく六軒の貸家をリストアップしたとこ
ろであった。
オフィスを出て、その六軒に片端から電話をかけると,どれもこれも既に契約済みで、
最後に「これはちょっと遠いけれど、そうかな、ま、念のためにメモしておくか」という
つもりで書いておいた一軒だけが残った。メモには、ヘミングフォード・グレイのマナ
ー・ハウス、家主は、Mrs.L.M.Bostonとあった。
電話すると、すぐに優しい上品な声の老婦人が出てきて、「ええ、ええ、まだ空いて
いますよ、どうぞ見においでください」と言った。翌日に訪ねることを約してその日はロン
ドンへ帰ったが、その時点ではちょっと遠いことではあり、そこに住むことになろうとは
思ってもいなかったのである。
次の日は、空高く晴れた秋の良日になった。夫人の言うには「ハンティングドン・ロード
を十五分ばかり走ると”セントアイヴィスへ”という標識がありますから、それを右に
折れて、少し行くと左に曲がる道があります、それを入ってずっと来ると、川に突き当たるので、
そこに車を置いて、川沿いの小道を歩いておいでになれば、すぐに分かりますよ」
というのであったが、果たしてそんないい加減な道案内で無事行き着けるだろうかと
少し不安を覚えながら、気持の良い田園の風景の中を走っていった。しかし、なるほど、
夫人の言うとおりで、当てずっぽうで進んでいくと道は行き止まりになり、そこに「The
River」という標識が立っている。
どうでもよいことだが、思うに、こういう定冠詞の使い方はいかにもイギリス的で、一つ一つ
の村が自己完結的に歴史を形作ってきた、そういう伝統がこういう書きぶりの中に
脈打っている。ついでに言うと、やがて私が住むことになった、この屋敷の離れの住所は
”The Annexe, The Manor, Hemingford Grey”というのであったし、そこから一番近い
町である、”St.Ives”には信号がたった一つしかなく、したがって、町の人々はこれを”THE
traffic lights”というのであった。
さて、ヘミングフォード・グレイののむらは中央にお決まりの”High Street”という道が
一本あって、その両側に少しばかりの古風な家が立ち並んでいる。店といっては、肉屋の
経営する小さな何でも屋が一軒、パン屋と酒屋を兼ねた店が一軒、雑貨屋を兼ねるニュー
ズ・エイジェントが一軒、パブと郵便局が一軒ずつ、それですべての、本当に小さな愛すべき
村である。そのハイストリートの突き当りが、くだんの「川」なのであった。その川は、
グレート・ウーズ川(Great Ouse River)というのであるが、普段はグレートと
は名ばかり、深い緑色の水を湛え、重くかすかに流れて行く小さな川である。水面には、
優しい女名前などの付いたキャビン付きのボートが幾隻も舫ってあって,ゆるやかに川波
に舷側を打たせている。どうやら、夏にはこの川を上り下りして、のんびりと船遊びをする人がいるらしい。
川の向こう側は一面の牧草地で、遠くに黒々とした森が地平を画している。森の上に
ひときわ鋭く空に突き刺さっているのは、あれは隣村の教会の尖塔であろう。
川のこちら岸には、二人が並んで歩けるほどの幅の遊歩道が続き、左手の煉瓦塀に沿って
かすかに曲がりながら遠ざかって行く。
なるほどそこからは車では行かれないので、私は車を乗り捨てて、遊歩道を川に沿って
歩いて行った。折りしも、向こうから大きな犬を歩ませながら近づいてきたおばあさんに
「The Manor はどちらでしょう?」と尋ねると、彼女は輝くように微笑み、「ええ、それは
この辺りで一番美しいマナーですのよ。さあ,私がご案内しましょうね」と言って、先に
立って歩きだした。ほどなく川岸の煉瓦塀に設けられた鋳鉄製の小さな開き戸を指し示すと、
さあここです、というように再び微笑みかけ、おばあさんはまた大きな犬をつれて
もと来た方向へ引き返していった。
鉄扉ごしに中を見ると、広々とした芝生の庭には、王冠や鷲の形に美しく刈り込まれた
櫟の樹(Ywe Tree)が、視線を館の方へ導くように道に沿って並び、その道の向こうに
三階建ての古い煉瓦館が見える。一階の窓は緑の生垣で縁取られ、横の壁と入り口のところは
白い漆喰で覆われている。私は、信じがたい思いで、そっと扉を開けて、恐る恐る
中へいっていった。
玄関の脇の小さな植え込みのところで、ずいぶん大柄ながっしりした体格のおばあさんが
何やら大きな黒いスコップを手に地面を掘り返しているところであった。これが一連の
「グリーン・ノウ物語」の作者として世界的に名高い女流作家ルーシー・マリア・ボストン
夫人だったのであるが、その時の私はグリーン・ノウもボストン夫人も恥ずかしながら
全く知らなかった。
近寄っていって「私、昨日電話を致しました、林ですが」と告げると、夫人はハッとし
たように振り返り、ああ、よくおいでになりました、道はすぐわかりましたか、といいながら
私を芝生の真ん中の、家全体が良く見渡せる所へ連れて行き、「これは、十二世紀の
初め一一二〇年に造られた、この国で最も古い家の一つです。」とこともなげに言うので、
私は殆ど腰を抜かしそうになった。一一二〇年といえば日本では平安時代、例の源平合戦
よりもまだ前のことで、本当だとすればこれはえらいところへ来てしまったぞ、と思った。
しかし、知らないというのは恐ろしいもので、私は感心したというよりは、寧ろ、もしか
してある種の老人にありがちな、誇大妄想の類じゃあなかろうかと疑う気持も正直ないで
はなかった。なにしろ当時夫人は既に満九一歳の高齢だったのである。(尤も、見たとこ
ろも話す調子も全く若々しくて、その時は八十近い歳かな、としか思わなかったのだが)。
夫人の傍らに小柄な老人が立っていたが、これは彼女が「ワトソン」と呼び捨てで呼ぶ
庭師のワトソンさんであった(ワトソンさんは同じ村に住んで、毎朝この屋敷に通ってく
るのである)。彼は、見たところ七十位の白髪のおじいさんで、この家に専属の庭師として
四十三年間勤めてきたのだそうである。四十三年間!彼はその一生をこの庭の草木の
為に使い果たしてきたのである。ワトソンさんは、実直そのものの表情で、口許を綻ばせ
ると、かなりケンブリッジ訛りの強い英語で、ささやくように初対面の挨拶をした。
その日、ロンドンへ帰る道々、私はとつおいつ考えた。あの屋敷には、あのおばあさん
がたった一人で住んでいるそうだ。それにしてもあの場所は、昼間は良いとして、夜はさ
ぞかし真っ暗で、森閑として寂しいところであろう。冬はうんと寒いかも知れぬ、生活上
にも不便が多いであろう、もしかしたら、この古い館は、「呪われた館」かなにかで、殺されて
食べられてしまっても分からないかも知れぬ、などととんでもないことまで、それからそれと
脳裏をかすめるのであった。
しかしそれにしても、と私は脳味噌の中に去来するさまざまな思いを、エイヤッと払いのけた。
そうして、思い切ってイギリスでしか経験できない「物好き」に賭けてみよう、
と決心したのである。
翌日、再び夫人の住む館を訪ねた。「僕はここにすむことにしました」と話すと、彼女
はたいそう喜んで、今度は部屋の隅々まで案内し、「私は今まで、何冊かの小説を書いて、
それらは日本語にも訳されているので、日本人の知り合いも何人もいますよ」と言ったり
した。私の住む部屋は、日本風に言えば2LDKで、母屋に接続してドア一枚で行き来の
できる十二畳程のLDK、それに中庭を隔ててちょと離れ風に(といっても壁は母屋に
接しているのであるが)なっている六畳ほどの居間(Sitting Room)と四畳半くらいの天井
の低い寝室、という具合になっている。ちょうどこの通路を兼ねた中庭は母屋の台所の窓に
面し、いつも台所でコトコトと料理をする夫人の姿が見えるのである。とはいえ、キッチン
から居間へ行くときは、一旦ドアを開けて外へ出て、中庭を通って行くので、雨など
降ると傘をさして通わねばならなかった。因みに、この居間と寝室になっている場所は
このように改装する前は石炭置き場であったそうであるが、さらにその前、そもそもの淵源
をたずぬるに、もとはこの屋敷付属の「礼拝堂」であったそうな。「ですからね、あなたは
Holy Placeに住んでいることになりますよ。」といって、夫人はまたウォッホッホと高笑いを
するのだったが、それにしても礼拝堂を石炭置き場にしちまうというところが、
いかにもイギリス的ではある。
試みに「僕は掃除が嫌いですから、部屋を散らかしますよ」と言ってみると、「そりゃ
あなたの部屋ですもの、好きなだけお散らかしになって」、と夫人は朗らかに笑いながら
答え、事実ここに住んでいる間中、一度もこごとめいたことは言わなかった。
家賃は、概ね相場の三分の一ぐらいの破格の安さで、なんだか申し訳ないようであったが、そ
れでも彼女は「もっと安くしましょうか」などといって却って私を困惑させた。そればかりか
イギリスでは通常Depositといって日本の敷金にあたるようなものを約一か月分
くらい取るのだが、夫人はそんなものは要らないわ、といって受け取ろうとしなかった。
「もし備品を壊したりしたら、町のマーケットで買って補充しておいて下さればそれで良いのよ。
どうせ大した価値のあるものなんかありゃあしないのですもの」と彼女はいうのだったが、
その実、そこの台所に備え付けの食器ときたら、イギリス伝統の「Willow Pattern」の
ボーンチャイナで、ほとんどはヴィクトリア時代の骨董品、価値がないどころか、
日本に持ってくれば目の玉の飛び出るような値の、古めかしくも楽しい品ばかりなのであった。
一般に、イギリスでは家を借りるときはエイジェント(周旋屋)が間に入って、家の
現況や備品を事細かに書き上げた「Inventory」というものを立会確認の上交換し。立ち
退きの際に揉め事が起こらぬようにするのであるが、夫人はそんなこと、面倒だからよしましょう、
お互いの信頼(Trust)でね、といって、これも一向に気に掛ける様子がなかった。
この、いわば見ず知らずの東洋人を、まずはしっかり信頼する、という態度に私がどれほど
感動し力づけたれたか。私がロンドンで部屋を借りていたフレデリック・ローゼン博士
(ジェレミー・ベンサム研究の第一人者)にしても、、全くこんな調子であったから、私は
さすがに大国の民は大したものだと、重ねがさね感じいった。漱石なども下らない安下宿
でなくて、しかるべき上流の人の家に住まいを得たならば、倫敦塔で妙な妄想に耽ったり
せずと、ずいぶん違ったイギリス生活を送ったであろうにと、なんだかイギリスと漱石と
両方のために残念な気がしてくるのだった。
まもなく、新学期の歓迎パーティーがコレッジで開かれた。おなじコレッジのカーメン・ブラッカー女史が
「家はどこに決まりましたか」と尋ねるので、ヘミングフォード・グレイ村に、と答えると、彼女は一瞬眉をしかめて、
何でまたそんな不便なところにしたのか理解しかねるといった表情を隠さなかった。
「もっとも、私はあの村に良く知っている人がいますから、一度お訪ねになるとよいですね、
ルーシー・ボストン夫人といって、世界的に有名な女流作家なのだけれど・・・・・・」
と、そこまで聞いて私は驚いた(エッ、そんなに有名な人なのか、あのおばあさんは!)。
「いえ、実はそのボストン夫人のマナーに住むことになったのですが」
そういうと、今度はブラッカーさんがびっくりするばんであった。そうして、急に晴ればれとした
表情になって、言った。
「それはまあ、なんて素晴らしいことでしょう。あの方は今までいくつも子供のための
小説を書いているのですけれど、それが『グリーン・ノウ物語』といって、みなあの
『館』自体がモデルになっているのです。言ってみれば、その館が主人公なのです。それに
ボストンさんはまた、薔薇の古代品種の育種家としても著名のうえ、詩人でもあり、
パッチワークとお料理の名人でもありますのよ。でも一番良いことはね、ボストン
さんご自身、本当に心の温かな気持の良いお人柄ということですよ、ですから林さん、
あなたは間違いなくケンブリッジ中で一番、いえイギリス中で一番幸せな日本人に違いありませんよ」
ともあれ、こうして私は、不思議な縁に導かれて、グリーン・ノウの物語のなかに・・・・・
暮らすことになったのである。
住んでみると、この屋敷はおもっていたよりずっと暮らしやすかった。台所を兼ねた食堂には、
低い天井に一抱えもあるような黒々とした梁がとうり、ボイラーには四六時中熱い
お湯が沸いていて、自然と部屋を暖めている。イギリスに住んだことのある人は知っている
とおり、イギリスの家庭で、二十四時間お湯が沸いていて何時でも蛇口から熱湯が出る
などというのは、実は本当に稀有のことなのである。イギリス人は元来合理主義で、時に
はそれが行過ぎることもある。例えば給湯に関してなどその好例であって、ほとんどの
家庭では、ボイラーは一日の内のほんの数時間しか火がつかないようにタイムスイッチで
コントロールされている。だから。その時間を過ぎて風呂にでも入ろうものなら、途中で
湯は冷水に変じ、まず間違いなく風邪を引いてしまうであろう。しかも、たいてい給湯器
のタンクは驚くほど小さく、従ってうっかり台所の洗い物で湯を使い過ぎると、シャワーを
浴びるのにも事欠くという仕儀になる。(なにしろ、イギリスではホテルでさえそういう不愉快な
経験をすることが珍しくないのだ)、ボストン夫人のマナーハウスだけは違っていた。
『お湯ぐらいいつも沸かしておきましょうよ、たっぷりとね。だから、どうぞ好きなだけ、
存分にお湯をお使いなさい。ガス代は、そうね、三分の二は私、三分の一があなた持ち、
というのでいかが」と彼女は言うのだったが、実際は私のほうがたくさん湯を使ったことは
ほぼ間違いない。こうして、おかげで私はいつでもたっぷりと湯を使って洗い物をし、
毎日風呂に入って快適な生活を送ることが出来たというわけである。
食堂の北面には木製のサッシの入った古風な開き窓が二つ。その窓の下に
ダイニングテーブルがしつらえてある。木の椅子がちょとがたがたするのは、床がぶきちょに
波打っているせいであろう。
引越しを終えて、その木の椅子に腰掛け、北の窓を開けて夕方のお茶を飲んでいると、
遠く森の向こうの教会から、しきりに晩鐘を打ち鳴らすのが聞こえてきた。夕方の陰りの
中に沈みつつある向こう岸の牧草地では、なお帰らずにいる牛が数頭ゆっくりと草を食んでいる。
それはまったく、私たちの心の中にあえかに息づいている「憧憬の西洋」そのものの風景
なのであった。私はなかば放心状態で、しばらく、窓の向こうの夕景を眺めながら、この
日のことはいつまでも覚えておこう、と思った。
やがて秋が深まって一日一日と驚くほど日が短くなっていった。確かに冬の夜は暗く
長かったが、さりとて思ったほど寂しいということはなかった。ボストン夫人のもとのは
しょっちゅういろいろな友達が訪ねてきて、折々音楽会が催されたり、食事を共にしたりして、
館の中にはいつも和やかな空気が満ちていたからである。それらの事どもはまた別に書くことにしよう。
さて、こうして十二月の六日になった。
その夜は、良い月夜でしかも十四夜であった。太陽はこの季節には、地平近くをスッと
横ぎる程度なのだが、月は宵から出て、夜半には中空高く皓皓と照っていた。あまりに
良い月夜なので、私は夜も更けわたる頃、庭へ出てみた。ドアを開けると夜風は寒くない
程度にひいやりとして、食堂の石葺きの屋根が白く光るのが見えた。
「おや、霜・・・・・」
けれどもよく見ると、それは霜ではなく、屋根の上に降りた夜露に月光が射して冷たく
光っているのであった。
広い庭にはどこにもここにも月の光がくまなくて、木々も、芝生も対岸の牧草地も、
その月光の白さに染められているのが見渡された。庭の北の外れのイバラの藪をみると
枝一面に真っ白で、今度こそ本当に霜が降りてクリスマスデコレーションのように白く輝いていた。
「やっぱり、霜!」と、そう思って、そのイバラの枝に手を触れてみると、それは
またもや霜ではなかった。冬枯れの枝枝に月の光が宿って、どうしたって霜としか思えないほど
真っ白に光っているのだった。
そこまで行って、後ろをふりかえると、月はマナーハウスの大きなチムニーの左に、
ほんの少しかすみながらかかっていた。館の窓には、 燈が黄色く灯っている。夜更かしの
ボストン夫人は、まだ起きていて本でも読んでいるらしい。
その時、この月下の庭に立って、私は初めて知った。生まれてからこのかた。ずっと
東京に住んで、本当の月の光を知らずにいたことを。
思えば、
庭冴ゆる月なりけりな女郎花
霜にあいぬる花と見たれば
という西行法師の歌や、例のゆうめいな「牀前月光ヲ看ル、疑ウラクハ是レ地上ノ霜カト」 という
李白の詩の表現を単なる文学的誇張とばかり信じていたのだったが、恥ずかしいことである。
なるほど、むかし月はこのように地上に光を落としたのであったか。
翌る晩、その夜もまた、美しい満月が空にかかっていた。熱く火の燃える大きな暖炉の
前で、前の夜の月光の白さについて話すと、ボストン夫人は優しく微笑みながら静かな声で言った。
「そうね、もうずっと昔、わたくしがまだ子供だった頃、こういう美しい月の夜には窓を開けて
ベッドにはいったものだったわ。・・・・・どう言ったらいいかしらね、月の光をね、
まるで陽に照らされたように・・・・・、もっとも何も熱は感じないのよ、ただ、光が、こう
顔に当たっているのが目をつぶっていてもはっきり感じられたのだったわ。わたくしは
それが好きで、月の良夜はいつもカーテンを閉めずに月光にてらされながら眠ったものだったわね・・・・・」
それから、わたくしたちは満月の夜の狂気のことや。日本の月見の風習のこと、狼男や
月の兎のことなどをあれこれ話して、夜はいつのまにか更けた。部屋へ帰ろうとして窓の
外を見ると、気紛れな空はすっかり曇って、庭は漆黒の闇にとざされていた。 完
ボストン夫人の次の代のマナーハウスの様子が「グリーンノウ探訪」に描かれています。
:http://www.geocities.jp/urouro611/travel/green/green.html
テーマのページにもどる